マリー=セリー・アニャン:ふたつのアメリカの作家作家マリー=セリー・アニャンは、ハイチの首都ポルトープランス生まれ。1970年以来ケベック在住。2010年12月、獨協大学の招きで日本の複数の大学で講演を行うために来日した彼女に、フラン・パルレの読者のために講演で触れられたテーマのいくつかを再論していただいた。
 フラン・パルレ:奴隷制や植民地主義の痕跡を消し去ることはできるでしょうマリー=セリー・アニャン:それは難しいような気がします。なぜなら今日でも別の形をとって、そうしたやり方が生き続けているからです。最近、アンジェラ・デイヴィスの『民主主義の強制収容所』という本を読みました。彼女があるジャーナリストと行った長い対話が再録されているんですが、そこでデイヴィスは、奴隷制のもとで生きられた状況と、今日のマイノリティーが監獄のなかで生きる状況とを比較しています。人々のある部分がそっくり監獄に封じ込められ、たとえば投票する権利も認められず、彼らの声を聞いてもらうこともできずにいるわけです。そういう種類の人間を厄介払いするために、監獄に封じ込めることが社会のなかにメカニズムとして設置されているわけです。フラン・パルレ :それはアメリカ合衆国のことをおっしゃっているんですね?マリー=セリー・アニャン:アメリカ合衆国もそうですが、ある程度まではケベックもそうなんですよ。マイノリティーの若者たちは、犯罪へと方向づけられていて、彼らは似たような状況を生きているともいえるからです。つまり彼らはそういった道へと誘導されているんです。それは学校ですでに準備されます。子供たちが学校で誰にも聞いてもらえなかったり、支援も用意されていないような状況に置かれると、どうなると思いますか?ドロップアウトしてしまうわけですよ。言葉の問題や、社会問題や、親の失業といった問題に直面した子供たちはね。だってほかにどうしようもないんですから!たしかにカナダはある程度まではかなりリベラルな社会で、アメリカ合衆国の社会とは許容される範囲が違います。でも、それもやはり程度問題であって。カナダであれ、フランスであれ、どこであれ、わたしたちの社会を規定しているのは同じシステムなんです。
フラン・パルレ:奴隷制や植民地主義の痕跡を消し去ることはできるでしょうマリー=セリー・アニャン:それは難しいような気がします。なぜなら今日でも別の形をとって、そうしたやり方が生き続けているからです。最近、アンジェラ・デイヴィスの『民主主義の強制収容所』という本を読みました。彼女があるジャーナリストと行った長い対話が再録されているんですが、そこでデイヴィスは、奴隷制のもとで生きられた状況と、今日のマイノリティーが監獄のなかで生きる状況とを比較しています。人々のある部分がそっくり監獄に封じ込められ、たとえば投票する権利も認められず、彼らの声を聞いてもらうこともできずにいるわけです。そういう種類の人間を厄介払いするために、監獄に封じ込めることが社会のなかにメカニズムとして設置されているわけです。フラン・パルレ :それはアメリカ合衆国のことをおっしゃっているんですね?マリー=セリー・アニャン:アメリカ合衆国もそうですが、ある程度まではケベックもそうなんですよ。マイノリティーの若者たちは、犯罪へと方向づけられていて、彼らは似たような状況を生きているともいえるからです。つまり彼らはそういった道へと誘導されているんです。それは学校ですでに準備されます。子供たちが学校で誰にも聞いてもらえなかったり、支援も用意されていないような状況に置かれると、どうなると思いますか?ドロップアウトしてしまうわけですよ。言葉の問題や、社会問題や、親の失業といった問題に直面した子供たちはね。だってほかにどうしようもないんですから!たしかにカナダはある程度まではかなりリベラルな社会で、アメリカ合衆国の社会とは許容される範囲が違います。でも、それもやはり程度問題であって。カナダであれ、フランスであれ、どこであれ、わたしたちの社会を規定しているのは同じシステムなんです。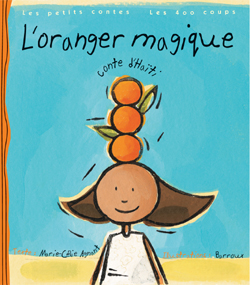 フラン・パルレ:あなたはいとも軽快に、大人向けの深刻な作品と、子供向けのお話を書き分けていらっしゃいますよね…。マリー=セリー・アニャン:たしかに子供向けのお話ではありますが、子供にはすこしハードルの高い文学でもあります。たとえば、わたしが書いた二つの小説は、9歳から読めますけれど、大人だって読みます。抑圧や、政治体制や、弾圧や、亡命といったことが語られていて、子供たちもとても喜んで読みます。お話は、わたしが子どもたちに謝意を表明したいという欲求から生まれました。というのも子供たちは教室を訪れるわたしに対してとても寛大で、わたしが子供たちとの交流でもたらすものにとても感謝してくれます。そこでお別れをする前に、みんなに何か贈り物をあげましょうってね。それでお話をしてあげるようになったのです。それからあれこれ、そうしたお話を書くようになったんです。だから、わたしの書き物が多様になったのは、そうした幸福な連鎖の結果なんです。
フラン・パルレ:あなたはいとも軽快に、大人向けの深刻な作品と、子供向けのお話を書き分けていらっしゃいますよね…。マリー=セリー・アニャン:たしかに子供向けのお話ではありますが、子供にはすこしハードルの高い文学でもあります。たとえば、わたしが書いた二つの小説は、9歳から読めますけれど、大人だって読みます。抑圧や、政治体制や、弾圧や、亡命といったことが語られていて、子供たちもとても喜んで読みます。お話は、わたしが子どもたちに謝意を表明したいという欲求から生まれました。というのも子供たちは教室を訪れるわたしに対してとても寛大で、わたしが子供たちとの交流でもたらすものにとても感謝してくれます。そこでお別れをする前に、みんなに何か贈り物をあげましょうってね。それでお話をしてあげるようになったのです。それからあれこれ、そうしたお話を書くようになったんです。だから、わたしの書き物が多様になったのは、そうした幸福な連鎖の結果なんです。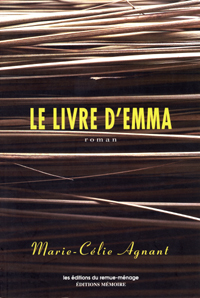 フラン・パルレ:それにお話はハイチの遺産でもありますよね。マリー=セリー・アニャン:まったくそのとおりです。お話は遺産です。ハイチにいたころは、わたしがお話をすることはありませんでした。むしろ人に物語を聞かせてもらっていたんです。それが突然、わたしは書いているけれど、書くこともまた物語ることだって発見したんです。それに、わたしは書くときには、いつも文章のリズムを見つけるために声に出して書きます。わたしはまったく語り部だと思いますよ!わたしのある小説についてベルギーで博士論文を書いた人がいます。『エマの書』に関する「語り部の言葉」という論文なのですが、時代の奥底からやってくる物語を複数の声が語る点を論じています。アフリカの海岸からアメリカへ連れてこられた女性たちの物語です。そしてアメリカに住む子孫の最後の一人が自分の話を伝える相手は、おなじ家族の血筋に属してはいないけれど、やはりその物語の継承者になるのです。お話とはだからそういうことです。つまりそれは継承された言葉なのです。2011年1月インタヴュー:エリック・プリュウ翻訳:藤田朋久
フラン・パルレ:それにお話はハイチの遺産でもありますよね。マリー=セリー・アニャン:まったくそのとおりです。お話は遺産です。ハイチにいたころは、わたしがお話をすることはありませんでした。むしろ人に物語を聞かせてもらっていたんです。それが突然、わたしは書いているけれど、書くこともまた物語ることだって発見したんです。それに、わたしは書くときには、いつも文章のリズムを見つけるために声に出して書きます。わたしはまったく語り部だと思いますよ!わたしのある小説についてベルギーで博士論文を書いた人がいます。『エマの書』に関する「語り部の言葉」という論文なのですが、時代の奥底からやってくる物語を複数の声が語る点を論じています。アフリカの海岸からアメリカへ連れてこられた女性たちの物語です。そしてアメリカに住む子孫の最後の一人が自分の話を伝える相手は、おなじ家族の血筋に属してはいないけれど、やはりその物語の継承者になるのです。お話とはだからそういうことです。つまりそれは継承された言葉なのです。2011年1月インタヴュー:エリック・プリュウ翻訳:藤田朋久

マリー=セリ−・アニャン、童話本『恋する魚の伝説』著者
投稿日 2011年1月1日
最後に更新されたのは 2023年5月25日

